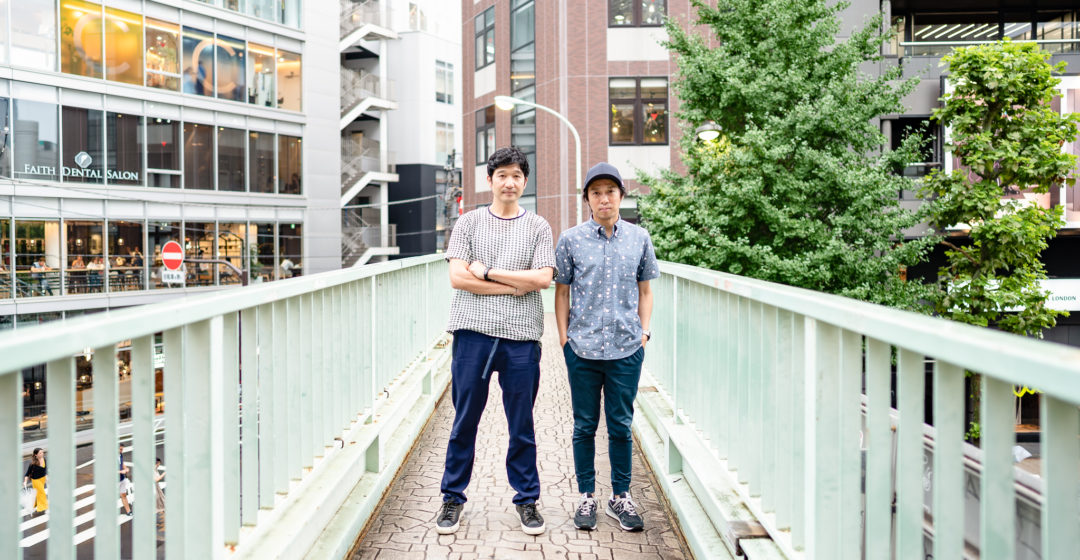
INTERVIEW
FREESTYLE FOR LIFESTYLE Vol.3 松山智一 ✕ 野上大介
「横乗りで培われた世界的アーティストの感性」
2019.09.11
能動的かつ自由にラインを描き、独自性あふれるトリックを繰り出すライディングスタイルを通じて、スノーボーダーであり、いち個人としてのライフスタイルが育まれていくのではないか。こうしたフリースタイルスノーボーディングの根幹をひも解くべく、スノーボーダーにして各界で活躍する有識者を招いた対談企画を用意した。第3回目のゲストは、現在ニューヨークにスタジオを構え、各国の美術館やギャラリーで個展を開いたり、かのビル・ゲイツも彼の作品をコレクションするなど、世界的に注目を集めているアーティスト、松山智一氏だ。
アートの最先端都市・ニューヨークに飛び込んだ
松山智一(以下TM): どこで僕のことを知られたんですか?
BACKSIDE編集長・野上大介(以下DN): ヨッシー(太田宜孝)から聞いていました。彼が手掛けているUNFUDGEからサポートされていて、もともとはコメカミチョッパーズのメンバーだって。
TM: あぁ、なるほど(笑)
DN: アーティストに転身されたキッカケは何だったんですか?
TM: 22、3歳のとき、すでに僕は全身スポンサードされていて雑誌の撮影などにも参加していましたが、スノーボードでどこまで上を目指せるんだろうと思い、大学を1年間休学して、さらに集中して取り組むことにしたんです。その年の6~9月は(アメリカ・マウントフッド)ティム・ウィンデルズのキャンプでみっちりとコーチ兼通訳をしながら滑り込み、10月半ばからコロラドにも行きました。それで、さぁ、これから本格的なシーズンだってときに大ケガをしてしまったんです。
DN: どんなケガだったんですか?
TM: 足の複雑骨折です。しかも、バインディングを装着せずにスケートトリックをしたときに(苦笑)。歩けるようになるには手術だけでなく、10ヶ月にもおよぶリハビリが必要で……。ただ、いつの頃からか自分の中で、スノーボードは一生続けられないものと思っていたのかもしれません。それで入院しているときに考え抜いた結果、スノーボードやジャケットなどをデザインする仕事だったら一生やっていけるかもしれないと思ったんです。
DN: それまでにデザインの仕事は?
TM: ヨッシーがSALOMONに在籍していた頃、ティムのキャンプで彼からボードに絵を描いてくれって頼まれたんです。それを当時中学1年の中井タカ(孝治)が羨ましそうに見ていて。その後、タカがINFINITYからシグネチャーボードを出すときに、「マツくん、僕の板のデザインをやってくれない?」って頼まれて引き受けたことがあります。
DN: それがデザイナーとしての初仕事だったわけですね?
TM: そうです。ありがたいことに評判がよくて、その翌年にはINFINITYのボードすべてのデザインを担当しました。その後は同ブランドのクリエイティブディレクターとして、雑誌広告や展示ブースのレイアウトなど、すべてのクリエイティブを任されるようになりました。そんな仕事をしながらニューヨークに渡ったわけです。
DN: そこからアーティストとしての活動が始まるわけですね。
TM: はい。ただ、それまでアートやデザインに関してちゃんと学んだことがなかったから、まずは学校に通って勉強し直しました。そんなときにKAWSなど同世代のアーティストたちと会ったんです。彼を見たとき、「え? こんな人生アリなんだ?」って思いました。自分の好きに描いた絵が作品として世の中に回り、それで生計を立てていたから。それがキッカケで自分を見つめ直したんです。中途半端な気持ちでデザインをやって日本と関わりを持っていると永久にそこから抜け出せなくなると思い、それまでの仕事をすべて辞めたんです。2005年くらいのことですね。
DN: もともとはスノーボーダーとして表現する側の立場だったわけじゃないですか? その後はクライアントのためにデザインし、そして自由に表現するアーティストになった。それって再び、スノーボーダーのようなマインドに戻られた感覚でしたか?
TM: それはあると思いますね。僕は表現活動に特化したいがためにニューヨークに渡りました。だったら、もっと自分にしか創り出せないアートを突き詰めようって。
DN: 通ずるところがあるんですね。

TM: そうですね。たとえばインディグラブって、それひとつに何年間もこだわることができるじゃないですか? それってアートに通ずるところがあると思っていて。ひとつのグラブなのに極限まで追求して、誰も見たことないスタイルで自己表現する。難易度の高いトリックに注目が集まりがちですが、そうじゃないところに自由な表現っていうものがあると思うんです。また、スノーボーダーって自分のアイデンティティをスタイルとして出すじゃないですか? だからこそ、僕もニューヨークのアートの世界では、日本人っていうマイノリティのアイデンティティを最大限に翻訳できる作品をアウトプットしないと意味がないと思いました。そして、等身大の自分が然るべき方法でアプローチするため、自分なりの手法を考え始めたんです。
DN: 向こうのカルチャーに染まることなく、日本人として作品を生み出すことにこだわったわけですね。
TM: そうです。アメリカのカルチャーに日本人としてどう入り込めるのか模索していました。
DN: スノーボードでも日本人として世界に挑む厳しさについて、僕はこれまで10年以上に渡って取材してきたカズ(國母和宏)から何度も聞いてきました。その世界の壁を突破するには膨大な時間とパワーが必要だ、と。松山さんがニューヨークに渡られた当初はそういった感じだったんでしょうか?
TM: 今もその世界の壁と戦っていますよ。それが自分のモチベーションのひとつになっていますからね。スポーツ界だと僕たちの世代あたりから世界の壁はブレイクスルーされてきたと思うんです。同い年の中田ヒデ(英寿)君がサッカーで、野球だったら野茂(英雄)さんだったり……現在はスノーボードでも世界大会で日本人が優勝してますよね? だけど、文化の世界ってまだまだなんです。そこが今の自分が突破したいと思うところ。スポーツもそうなんですけど、アメリカで生まれたものに対して僕たち日本人が結果を出そう思えば、彼らの倍できないといけないと思うんです。
DN: 同じことをカズも言ってました。
TM: そこには、文化の壁、言語の壁、そして肌の壁があると感じますが、ただ泣き言を並べるくらいならニューヨークに来なけりゃいいじゃん?って話になるので。
DN: カズは世界の壁を乗り越えて、昨年12月にライダー授賞式であるRIDERS POLLでRIDER OF THE YEARを獲得しました。
TM: 本当にすごいことですよね。うれしくなって受賞したときの映像は何度も繰り返して観ました。
DN: 1990年代の日本のスノーボードシーンから考えると想像できないことを成し遂げましたよね。
TM: 本当に! あと、僕がニューヨークにいるときに、アメリカのTRANSWORLD SNOWBOARDINGのカバーを(布施)タダシ君が獲得したのも見ました。それを糧に自分も頑張らなきゃと思ったのを覚えています。
作品を届けることこそアーティストの仕事
DN: 先ほどの話にあったように、一度すべてのシャッターを閉じた状態になられてから今まで、スノーボード関連の仕事はされなかったんですか?
TM: それが、ありがたいことに2008年だったかな? BURTONからボードのデザインをしてほしいという依頼がありました。スノーボードをやっていた過去は消した状態だったのに、僕の作品を見て、そして存在を知ってくれて、アーティスト・松山智一にオファーしていただいた。かなりうれしかったですね。
DN: 今後はスノーボード関連の仕事を再び?
TM: 今なら何をやっても自分がやってきたことに変な色がつかないという自信もあるので、それもアリなのかなと思ってます。あと、ニューヨークの著名なギャラリーや美術館で自分の作品を発表できるようになった今、また新たな景色が見えてきたんです。
DN: と、言いますと?
TM: これまで美術館のような場所で作品を発表したいと思ってやってきましたが、自分が親しんできたカルチャーと現在の自分がやっていることが段々と離れている気がしていて。今はもっと多くの人に見てもらえる、自分のルーツでもあるような場所にアートを出していきたいと思っています。
DN: 作品を届けることも大切にされているわけですね。スノーボードも同じように、多くのプロライダーたちは映像や写真を介して自己表現をしています。今はインターネットが台頭しているので、昔のようにスポンサーを集めて一年に1作品の大作を作ることは難しくなっていますが、とはいえムービーシーンはスノーボードにとって欠かせない存在です。

TM: 上手いスノーボーダーは大勢いますが、僕がスノーボードをやっていた時代から映像作品に出られる人は何かが違ってて。彼らは自分の哲学を持っていて、映像を残してカタチにする。それがスノーボードのプロフェッショナルだと思っていました。アートの話になりますが、僕は絵なんて誰でも描けると思うんです。でも、それをどうやって人に届けるか、どうやって人を感動させるかっていうアイデアがないと、また生活のすべてを捧げる覚悟がないと、その世界で残っていけないと思うんです。果報は寝て待てっていう言葉がありますが、実際は寝ていても何も来ない。アスリートでもトップにいる人たちはストイックですし、彼らは途中経過を誰にも言わない。それは、結果的に人を魅了すればいいということを知っているからだと思うんです。
DN: なるほど。
TM: 極端な話をすると、アートって売れなきゃ、ただのゴミだと思っていて。でも、売れることが正義じゃなくて、人の心を動かすことが正義で……。人の心を動かしたら作品になりますし、そうしたら絶対にお金はそのあとについてくるはずなんです。売れなかったら何かが間違ってる。そう突き詰めると、結果として売れるってことも正義なんですよね。売れなかったら、売れるために何をするべきかを考える。それを継続してやって、自分を証明することが表現だとも思っています。
歩んできた過去すべてが自分のレイヤーに
DN: 競技で点数を稼ぐスポーツになると、日本人は勤勉でルーティンワークも得意だから強いと思うんです。ただ、表現力に関しては少し乏しいのかなと思うんですが、いかがでしょうか?
TM: 日本人は組織力があると思います。でも、表現の世界では概念の部分であったり、独創性っていう部分が必要だったりするので苦手なのかもしれません。一方、僕がベースにしているニューヨークって異なる人たちの集まりなんです。
DN: 人種的に?
TM: 人種的にも文化的にも。だからこそ、他人の文化をイジってはいけないっていう意識を持つんです。そして、自分自身は何者なのかっていうのを考えさせられる。アメリカのスノーボーダーで次から次へと面白いヤツが出てくるのは、おそらく自分自身のキャラ設定が……。
DN: 上手いってことですね?
TM: だと思います。自分と人との違いを小さい頃からずっと考えてきたから。アメリカは移民が多い国だからこそ、ぶっ飛んだ人が出てきやすいのかなと思います。
DN: なるほど。単一民族で単一文化の日本ですが、松山さんはスケートボードやスノーボードをやっていたからこそフリースタイルマインドがあったんでしょうね。

TM: そうかもしれないです。僕は人生に無駄はないと思っていて。あのときスノーボードで出会った人たちが、結果的に今の自分を広げてくれたっていうか。スノーボードやスケートボードって昔から、僕にとっては人脈を広げるツールになっていたと思うんですよね。
DN: ちなみに最近は滑ってますか?
TM: 正月に高山に帰ると、毎年のようにPILEDRIVERの(オーナーである)前坂さんが雪山に連れて行こうとしてくれます。ですが、今は自分の手が商売道具なので、滑り出すと調子に乗ってケガするんじゃないかと不安で(苦笑)。実際にケガが原因でスノーボードから離れましたからね。でも、去年だったかな? 前坂さんやヨッシーに「明日、滑りに行こうぜ」って半ば強引に連れて行かれて(笑)、かなりひさびさに滑りに行きました。雪がすごい降っていたときで、結果的にめちゃくちゃ楽しかったです。
DN: ひさしぶりに滑ったことで、さらにスノーボードからインスパイアされた何かが今後の作風に加わったりするんでしょうか?
TM: ビジュアルの部分で加わることはないかもしれません。これまで自分の生い立ちを否定しないできたつもりなので、すでにスノーボードは自分の持っているレイヤーのひとつですし、自分の過去は作品に十分に出てるかなって。
DN: 最近はスノーボードも遊び方が増えていますが、松山さんに新たなレイヤーが加わることは?
TM: それはあると思います。スノーボードって、いろいろ考えられるものじゃないですか? ターンひとつでもグラブひとつでも突き詰められるから。
DN: 今後はもっと滑る回数が増えますか?
TM: もう40代ですし、そんなに攻めないでクルージングも楽しめるようになったとは思います。でも、怖いんですよね。山に何度も通ったら調子に乗っちゃいそうで(笑)。それに昔の仲間たちといると、例えばヨッシーなんですけど、彼は今もすごいスピードで滑るし、地形で軽くジャンプといっても10m以上は飛んだりするじゃないですか? しかも、ちょいちょい煽ってくるから(笑)
GUEST

(写真は本人より提供)
松山智一
Tomokazu Matsuyama
1976年生まれ、岐阜県高山市出身でニューヨーク在住のアーティスト。上智大学卒業後の2002年に渡米し、ニューヨーク私立美術大学院プラット・インスティテュートのコミュニケーションデザイン科を主席で卒業。現在はアメリカだけでなく、ドバイ、香港、ルクセンブルク、日本など各国の美術館やギャラリーで個展を開催している。また、その作品はマイクロソフトコレクションやドバイ首長国の王室コレクションなどにも所蔵されている。
text: Haruaki Kanazawa photos: Nobuhiro Fukami










