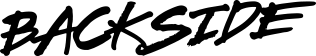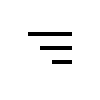COLUMN
トリプルコーク戦国時代の先頭を走る日本。その強さの核と、ハーフパイプが失ってはならないもの
2025.10.30
1998年の長野五輪で正式種目となったハーフパイプは、2002年ソルトレイクシティ五輪でアメリカ勢が表彰台を独占。2006年トリノ、2010年バンクーバー両五輪ではショーン・ホワイトが連覇を成し遂げ、アメリカは“絶対王国”として揺るぎない地位を築いた。
その背後で、日本人も世界最前線の現場に飛び出し、競技の本質と向き合っていた。2000年の「SIMS WORLD CHAMPIONSHIPS」で田原ライオが日本人として初の国際大会優勝を果たし、愛弟子・中井孝治が2002年ソルトレイクシティ五輪で5位。さらに、カズこと國母和宏は2003年の「BURTON US OPEN」で14歳にして準優勝を飾り、2010、11年には同大会を連覇した。ハーフパイプはアメリカだけの物語ではなく、日本人がそのページを書き換え始めたのである。
カズが競技人生を終え、映像表現へと舞台を移すと、そのバトンを受け取ったのが平野歩夢だった。14歳で「X GAMES」2位、2014年ソチ五輪で銀、2018年平昌五輪で再び銀。トリックの優雅さとエアの爆発的な高さを両立した滑りは頂点を射程に捉え、2021年「DEW TOUR」ではコンテスト史上初のFSトリプルコーク1440を成功。2022年北京五輪でもこの大技を決め、悲願の金メダルを手中に収めた。
この瞬間、ハーフパイプ競技は新たな段階へと進んだ。北京を境に、世界はいっせいに“トリプル時代”へ雪崩れ込んだのである。ショーンでさえ到達できなかった領域が勝つためのスタートラインへと変わり、ハーフパイプは未踏のフェーズへ突入した。
その後、オーストラリアのスコッティ・ジェームス、戸塚優斗、平野流佳、韓国のイ・チェウンらがトリプルコークを習得。バック・トゥ・バック(連続)や1620を公式大会で成功させた例はまだないが、その幕開けを告げる映像がSNSで飛び交っている。現在、日本人を中心としたアジア勢が、その進化を牽引しているのだ。
かつてのハーフパイプ大国・アメリカは、そのレベルから完全に後れをとってしまった。優斗が1620を、流佳が連続トリプルをSNSに公開した同時期、ジョーイ・オケソンとアレッサンドロ・バルビエリの両名がトリプルコーク1440を初成功させたというニュースを、アメリカの老舗メディア「SNOWBOARDER」が報じたことが、それを証明している。
アメリカが停滞した理由は、技術やフィジカル的な問題だけではない。ショーン・ホワイトという存在はあまりに巨大で、世界を前進させた半面、国内の競技文化は“次を育てる土壌”を広げられなかった。スターは生んだが、「文化の裾野」は作れなかったのである。いっぽうで日本は、トップの英雄を生みながらも、地道に土台を磨く文化を手放さなかった。
日本の強さの核心は、回転数ではなくリップ・トゥ・リップ(リップで踏み切りリップに着地する一連の動作)の正確性にある。着地が乱れないから加速できる。加速できるから高さが出る。高さが出るからスタイルが生まれ、結果として回転数にもつながる。「美しさが強さを生む」という思想こそ、日本が積み重ねてきた真価である。アジア圏が持つフィジカル的優位だけでは説明できない差が、そこにある。
いま世界は、1620という未知の領域へと踏み出している。この先、競技はさらに複雑化し、難易度のインフレは止まらないだろう。
しかし、ハーフパイプの価値は回転数だけではない。重力に抗うラインの美しさ、余白を感じるスタイル、観る者の心を揺さぶる表現──そこに宿る“美”こそ、この競技の根源である。
トリックが進化しても、文化まで失ってはならない。むしろ日本には、美と強さを兼ね備える競技観を未来へつないでいくだけの土台がある。
text: Daisuke Nogami(Chief Editor)
photo: The Snow League/Dasha Nosova